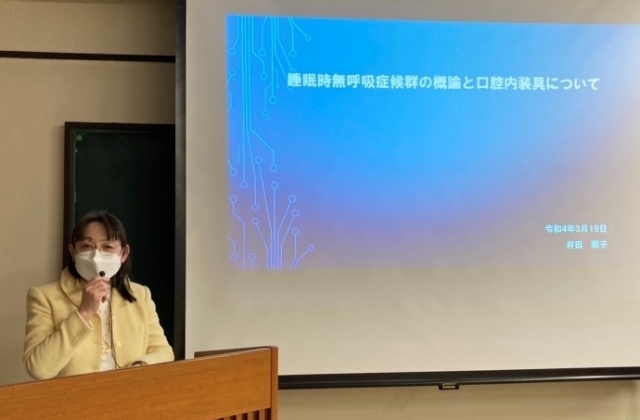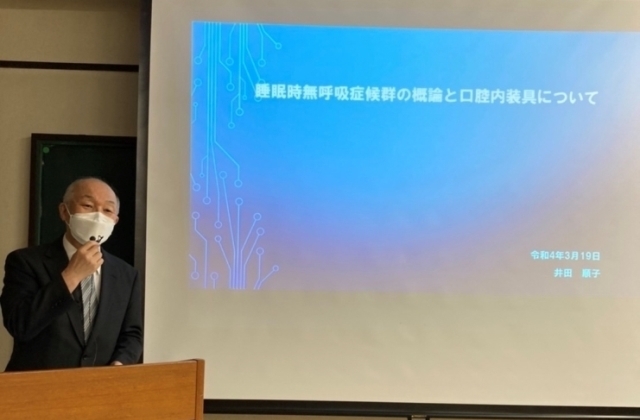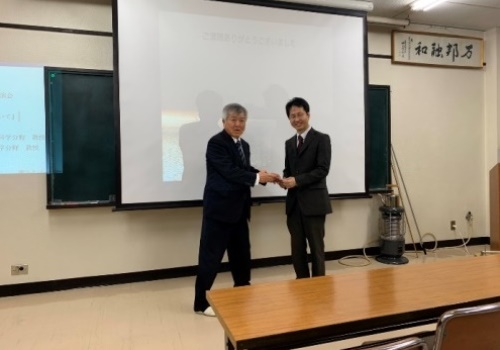令和5年度 太田新田歯科医師会学術講演会
日時 令和5年11月25日(土) 18時~20時
講師:岩野歯科クリニック 岩野 義弘 先生
演題:包括的歯周治療における歯科医師と歯科衛生士との連携
会場:太田新田歯科医師会 第一会議室
太田新田歯科医師会では年に一度、会員に向け講演会を開催しています。コロナ禍の影響もあり3年ぶりの開催となりました。

今回は岩野歯科クリニック(東京都)岩野義弘先生に包括的歯周治療について御講演をしていただきました。
歯周病はプラーク中の細菌感染によって生じる慢性炎症性疾患。
同時に日々の不良な生活習慣が関連する生活習慣病の一種ともいえます。
歯周治療の大きな目的の一つがプラークリテンションファクターの除去とプラークコントロールのしやすい口腔内環境の獲得とにことでした。
また感染源の除去のみならず、生活習慣の改善指導など様々な場面において歯科医師と歯科衛生士の連携が重要となってくるとのことです。
症例や文献を基に岩野先生が実際に行っている診療、歯科衛生士のブラッシング指導方法や口腔内清掃の勘所など日々の臨床に役立つ講演でした。

文責 学術医療管理委員会 渡木 澄子